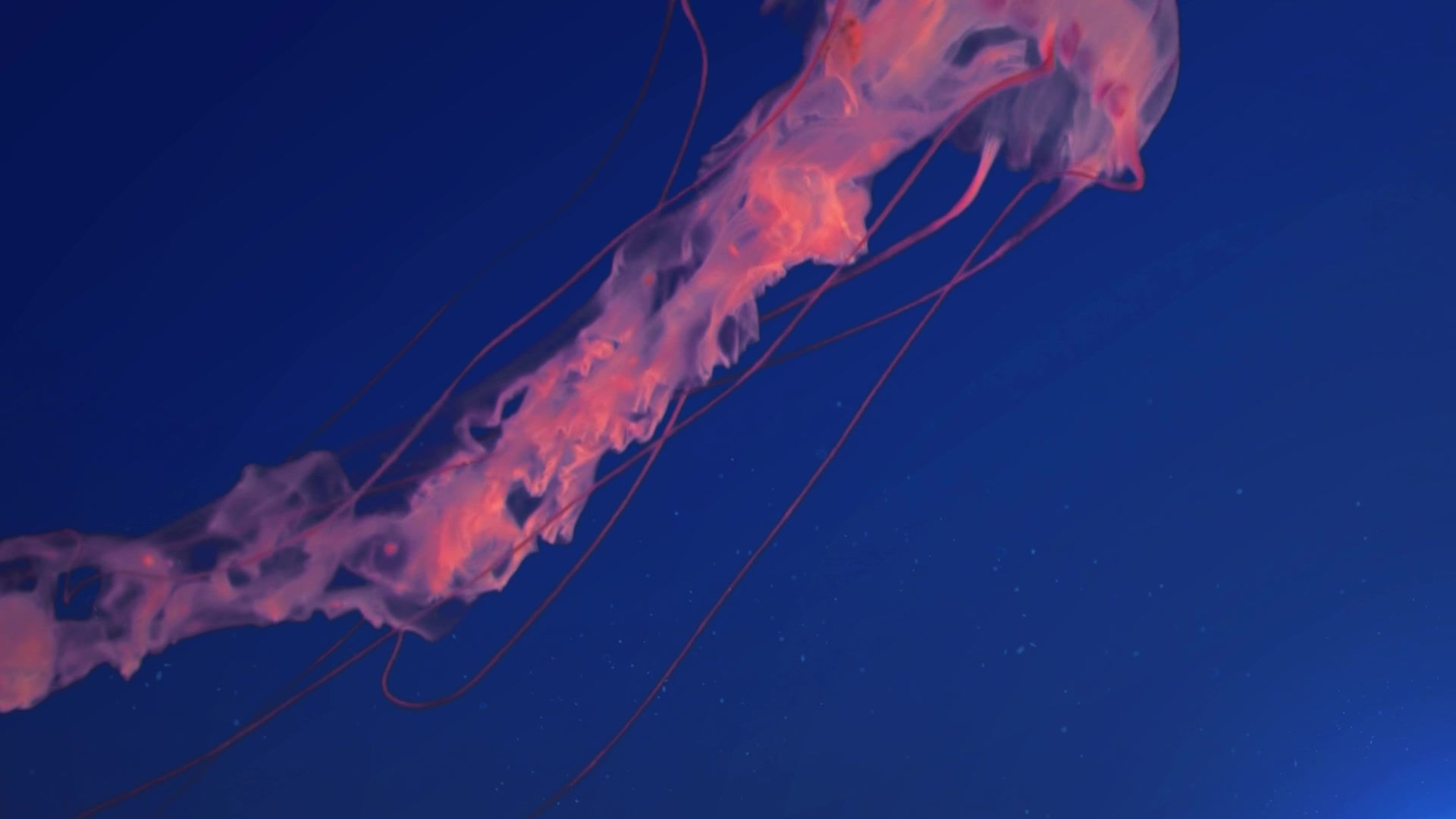
第3節 入試改革
入試多様化の実態
入試の多様化では「人物本位の選考」などの建前が語られているが,本音は大学経営の安定,教職員の雇用確保,学生の就活である。
実際,AO枠,数学なし枠が増えれば一般枠の定員が減る。受験難易度が維持され,受験料収入が安定し,教職員の雇用が守られる。有名大学に低学力学生が紛れ込み,バイトと人脈づくりと就職準備に励む。今の大学は学問の場ではなく就活の場である。
AO枠は公然裏口入試である。低学力AO学生の混入は真面目な学生の信用も低下させている。コネと女子力で有名大に入り,コピペ論文で博士号を取り,有名研究機関に入ることもできる。国家試験の出題者から模範解答を得ることもできる。労組幹部の高校教師が同僚の協力を得て子の内申点を上げる。偽装ボランティアで実績をつくる。自己推薦文と面接の想定問答は小論文講師が取材して書く。偽装ボランティアは合格後に消滅する。実例は多数ある。
大学の入学を厳しくすれば高校教師の権限が増える。大学の卒業を厳しくすれば大学教師の権限が増える。司法試験を法科大学院の教授が作れば情報が漏れる。不正をなくすためには第三者による客観的な評価が必要である。
慶應大経済学部は90年に数学なし受験を認めた。数学受験組は理論経済学,金融論,ゲーム理論,金融工学,計量ファイナンス,応用ミクロ経済学,現代マクロ経済学,数理経済学などを普通に学ぶ。一方,数学なし組は開発経済学,労働経済学,財政社会学,環境経済学,経済地理学,経済学史,経済思想史,国際貿易論,国際金融論などを学ぶが,数学からは逃げ切れない。
数学なし組の多くは公務員の数的処理や企業のSPI非言語ではじかれる。だが,一部はそれもコネで乗り切る。その分,国や企業は人材を失う。
理工学部愛智学科
プラトンは「幾何学を知らざる者」の入門を禁じた。実際,哲学と数学は不可分である。
たとえば,正多面体を考えたのはピュタゴラスであり,5つに確定させたのはプラトンである。デカルトは変量(変数)を導き,ライプニッツは座標を考えた。インドの「須弥山の階段」(Meru-prastaara)は「パスカルの三角形」として確率論の基礎となった。
数学なしの哲学科では哲学史や原典購読が中心となる。だが,哲学史は歴史であり,原典購読は文学である。美大に実技がなく,美学・美術史,美術教育,美術鑑賞を中心に学ぶようなものである。美学・美術史は文学部,美術教育は教育学部,美術鑑賞は趣味である。スキー教室に実技がなく,スキーの歴史だけ説明されて帰されたら普通は怒る。
「カントはこう言った」は哲学ではなく,引用である。現代的な問題を「カントはこう考えるだろう」と想像し,さらに「自分はこう考える」と結論づけるのが哲学である。論理的思考力が不可欠である。
フィロソフィアとは,上智or智慧(sopia),知恵(wisdom),知識(kowledge)のsophiaを愛することである。本来は愛智と訳すべきである。だが,西周が哲学と訳して以来,「哲学」はわけのわからないものの代名詞となった。
哲学科は愛智科に改名し,受験では数学を必須とするべきである。愛智学部を設置するのが大変であれば文学部哲学科を理工学部愛智学科に移せばよい。愛知県の大学にお願いしたい。
演繹法と帰納法
教科書に書いてあること,ネットで検索できることは既知事項である。既知事項を多く知る博識者(はくしきもの)を集めても新しいものは何も生まれない。大学入試から国会質問までクイズごっこの現状は情けない。IT時代の今,博識者に聞くより検索した方が早い。
教科書に書いてないこと,ネットで検索できないことが未知事項である。学問は既知を利用して未知を既知にする。既知の習得は学習である。既知の整理・暗記は趣味である。
事前知識を多く必要とする問題は悪問である。その知識は実社会では検索する。良問は問題文中の情報から答えを導ける。悪問が減れば資産格差や地域格差が減り,論理的思考力の勝負となる。
解答の各段階では読解力・分析力・表現力として発揮される思考の方法は演繹法と帰納法に分かれる。
演繹法は少ない法則から多くの結論を導く方法である。デカルトが提唱した。A組(学究人材),G組(世界人材)の選抜には演繹試験が不可欠であるが,無名高から私大文系に進んだ人は演繹力に欠ける。
算数の文章題,数学,将棋,囲碁,チェス,連珠,オセロは演繹試験の例である。作問が間に合わなければ中学受験算数過去問,高校受験数学過去問,SPI非言語などでよい。試験要項に公式を載せ,その公式を使って解く問題を出してもよい。科学五輪出場者は飛び級の大学生でよい。将棋,囲碁,チェスを中学受験の選択科目にすれば天才の早期発見につながる。
帰納法は多くの情報から結論を導く方法である。フランシス・ベーコンが提唱した。荷物が多く機動性に欠ける人は前IT時代にもいた。だが,再現に要する費用が安いものを破棄できなければごみ屋敷である。
問題文中に大量の情報を載せる帰納試験が有効である。文科省の高大接続システム改革会議で示された「問題発見・解決力のための分析的読解による連動型複数選択問題」はその例である(「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」の主な論点整理(検討・たたき台,15年6月配布)。作問が間に合わなければ辞書持ち込み可でもネット検索可でもよい。普通の長文問題でもよい。
今はプログラム開発も演繹法(ウォータホール・モデル)と帰納法(プロトタイピング・モデル)とその混合(スパイラル・モデル)である。コンピューターが発達しても正解の一意性はなく,近未来は優秀な人材とコンピューターがライバルとなる。
女子の底上げ
90年の国連ナイロビ将来戦略勧告は,指導的地位に女性が占める割合を「95年までに30%以上,00年までに50%以上」とした。安倍政権も「20年までに30%以上」とする。
野田聖子(自民党の前総務会長)はクオータ制(人数割当制)を主張する。米国のアファマティヴ・アクション,日本のポジティヴ・アクション,フランスの県議選がこれに当たる。
フランスでは男女ペア候補に投票する県議選が15年に始まった。98県で2054組4108人が当選したが,女性議長は8人にとどまった。当選回数を重ねた男性が議長になったためである。
高市早苗(総務相)は無能な女性を登用する逆差別に反対する。実際,女子の学力は低い。12-15年の科学五輪(数学,物理,化学,生物学,地学,情報,地理)出場人数は灘(兵庫)25,筑波大附駒場(東京)24,開成(東京)16,広島学院5,白陵(兵庫)4,栄光学園(神奈川)4,大阪教育大附天王寺3,大阪星光学院3である。白陵と大阪教育大附天王寺は化学に強く,大阪星光学院は物理に強い。この8校は全124人の68%を占める(のべ人数,開成中は開成に含む)。うち,女子は5人(4%)に過ぎない。囲碁には謝依旻六段(台湾出身),王景怡二段(王立誠九段の娘),藤沢里菜三段(藤沢秀行名誉棋聖の孫)がいる。将棋は西山朋佳三段,里見香奈三段,加藤桃子1級しかいない。
今活躍する女子をパイオニアとして裾野が広がるとよい。未来は教育がつくる。
正解の多様性と一意性
大学は正解の多様性を理解した人が別の可能性を探るためにある。1つの結論で満足する人は大学に進む必要もなく,実社会でも役立たない。
を矛盾という。形式論理学である数学では矛盾と非合理は同義である。だが,弁証法では矛盾も正解である。東洋では古代インド哲学や仏教に弁証法がある。西洋ではエレア派が弁証法を始め,ヘーゲルが体系化した。
高校では「三角形の内角の和は180度」と教えるが,地球表面では180度以上360度未満である。これは小学生でも理解できる。リーマン幾何学では180度以上360度未満,ユークリッド幾何学では180度,ボヤイ=ロバチェフスキー幾何学では180度未満と習う。
大学受験では形式論理学とユークリッド幾何学が正解,弁証法と非ユークリッド幾何学は不正解である。ゆえに,高校生には正解の多様性を教えなければならず,受験生には正解の一意性を教えなければならない。
形式論理学で は○, は×である。ゆえに,「色不異空 空不異色 色即是空 空即是色」の般若心経は0点である。ソフトボールで盗塁したり,チェスで取った駒を使うのと同様である。これは採点の平等性を担保するためだけではなく,コンプライアンスである。だが,大学の弁証法の授業では「色即是空」は○である。野球の盗塁,将棋の持ち駒と同様である。
プラトンが『国家』で語るように,算術と幾何を知らなければ弁証法もない。他の正解 は第1正解 の先にある。実際,数学が得意な人が「 」と言うのは深みがあるが,数学が苦手で文学部に進んだような人が「 」と言うのは薄っぺらである。 の段階で挫折した人は学問としてではなく,生涯教育として を学べばよい。
高校・大学・就職の各段階
国際バカロレア(IB)の学習者の目標は「探求する人」「知識のある人」「考える人」「コミュニケーションができる人」「信念をもつ人」「心を開く人」「思いやりのある人」「挑戦する人」「バランスのとれた人」「振り返りができる人」の10である。これは高校在学中の教育目標の例である。
入試や就職試験では論理的思考力が重要である。雑多な知識を問う現行入試はSPIに劣る。文中から根拠を探す問題が多い北米のACT,SATが参考になる。一方,専門家登用の国家試験では専門知識を競うべきである。実際,医学知識のない医師,先例を知らない司法書士はあり得ない。
11年に国立情報学研究所(NII)などが始めた東ロボくんは21年の東大合格を狙う。東ロボくんは辞書や教科書,ウェブ上の情報を使って解答する。つまり,実社会も東ロボ君も検索可である。問題文中に必要な情報を書くか,入試を持込み可・検索可に変えるか,検索可能な知識を問題から外すか,いずれかが必要である。
実社会では現場に入らずに理屈ばかり言う人は役に立たない。現場の情報は検索できない。だが,すべての現場に入るわけにもいかない。ゆえに,現場との信頼関係を築く力が必要である。現場力は短時間の入試や就職試験では把握できない。だが,調査書重視ではコネと女子力の試験となる。現場研修は大学卒業前と就職後でよい。入試と就職試験で問うべき力はプラトン時代,デカルト・ベーコン時代と同様,論理的思考力である。