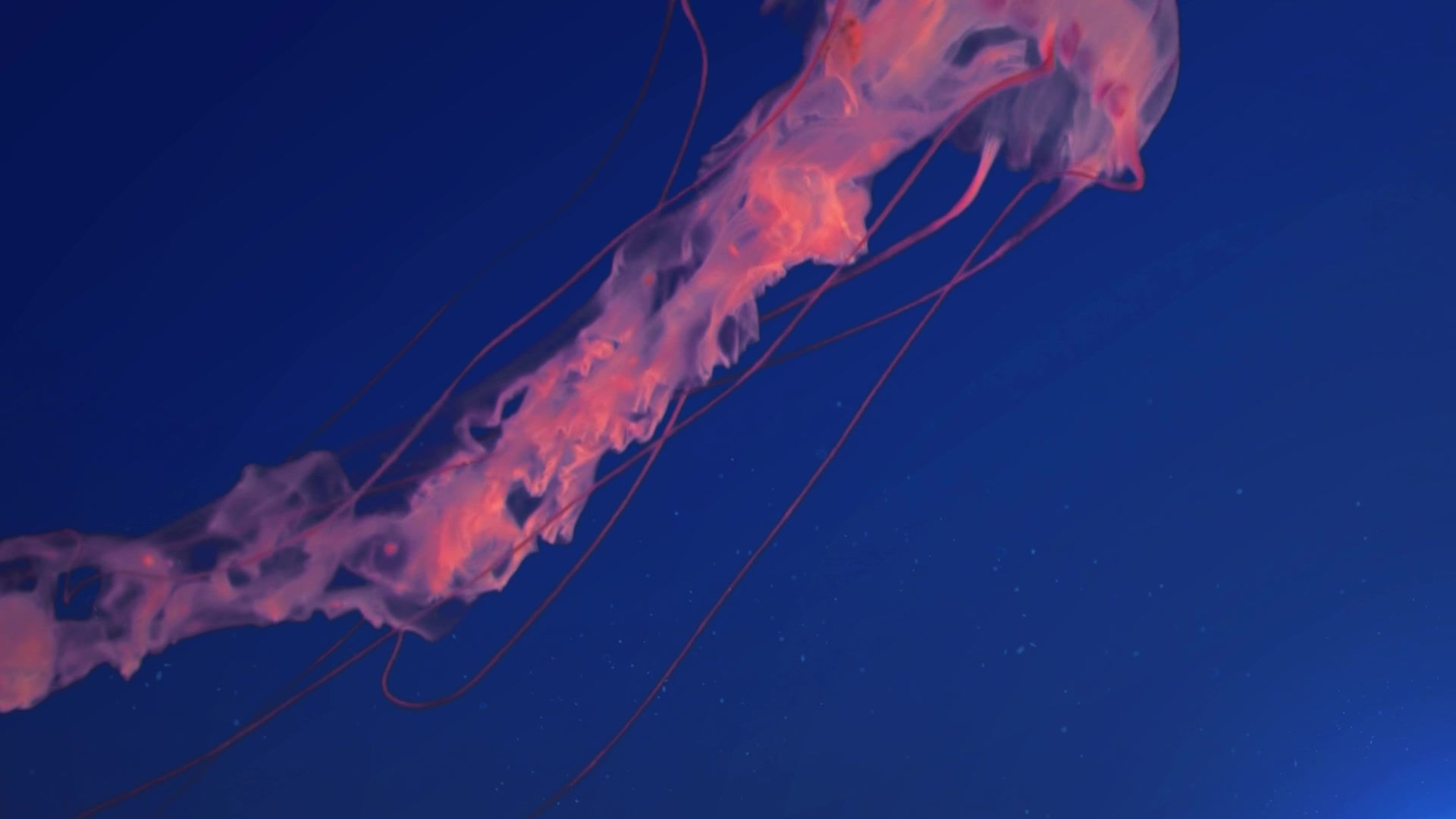
社 会 の 正 解i
第1章 所得の再分配
例1 人口5人の社会甲~丙がある。構成員の年収を低い順に並べて5次元ベクトルとする。
甲:(300万,300万,1千万,2千万,10億)
乙:(300万,300万,300万,300万,300万)
丙:(100万,100万,100万,100万,100億)
格差も平等も駄目
所得和は甲が10億3600万円,乙が1500万円,丙は100億400万円であり,丙が最大である。生産力の最大化を求める功利主義者は丙が最適と考える。たしかに,年収100億円の社長にとっては丙が最適である。だが,従業員の月収8万円は家賃・光熱水費・食費・交通費で消え,出産・育児のお金はない。
「全員主役」「全員1等賞」という社会には夢がない。平等主義者はパレート最適を知らない。甲で10億円の人も乙では300万円に甘んじる。だが,憧れのメジャーリーガーが10億円もらっても嫉妬しない甲の方が健全である。
ジョン・ロールズの正義論では,最も恵まれない人の利益を最大化し,その条件を満たす範囲で恵まれた人の利益を最大化する。最低所得者は甲=乙>丙,2番低所得者は甲=乙>丙,3番低所得者は甲>乙>丙であるから,最も健全な社会は甲,最も不健全な社会は丙である。甲はロールズ型社会,乙は平等社会,丙は格差社会である。
格差の尺度
ジニ係数(G係数)は甲0.78,乙0.00,丙0.80である。
所得の階級値をy(i),所得の平均値をμ,相対度数をp(i)とし,アトキンソン尺度(A尺度)を 1-[SUM{(y(i)/μ)^(1-ε)×p(i)}]^{1/(1-ε)}
で定義する。A尺度は甲0.97,乙0.00,丙1.00である。この2種は格差の尺度であり,数値が高い甲と丙は格差社会である。
相対的貧困率は甲0.40,乙0.00,丙0.00である。権力者以外平等の丙が貧困率0とは皮肉である。
格差が縮小しても生産力が縮小すれば社会の価値は上がらない。格差を表す尺度ではなく,社会の価値を表す尺度が必要である。
社会価値の尺度
アトキンソン価(A価)を 平均所得×(1-アトキンソン尺度)=[SUM{y(i)^(1-ε)×p(i)}]^{1/(1-ε)) で定義する。A価は格差が縮小しても増大し,平均所得が増えても増大する。「名目A価÷消費者物価指数」を実質A価という。
ε=2のとき,A価=1/{SUM(p(i)/y(i))は所得の調和平均であり,甲611万,乙300万,丙125万である。調和平均は並列回路の抵抗,旅人算の往復の平均速度などでおなじみであり,中学受験生でも計算できる。
所得を変えず,低所得者の原占有率を拡大して高所得者の原占有率を縮小する。人数の累積度数がp~qの階級の階級幅を(r^q-r^p)/(q-p)倍する。「原所得×改定後占有率」の総和をロールズ価(R価)とよぶ。「名目R価÷消費者物価指数」を実質R価という。
占有率を変えずに原所得を(r^q-r^p)/(q-p)倍して「改定後所得×原占有率」の総和を求めても数学的に同等である。 人社会では 番低所得者の原所得を{1-r^(1/n)}×{r^(1/n)}^(1/k)/(1-r)倍する。
r=1/10万のR価は甲317万,乙300万,丙190万である。r=0のR価は最低所得者1人に依存するため,社会全体の性質を表さない。
ε=2のA価やr=1/10万のR価は庶民感覚の社会価値を表す。
所得再分配の実例
例2 厚労省「所得再分配調査」(世帯別)
96 99 02 05 08 11年
G係数(当初所得) 0.44 0.47 0.50 0.53 0.53 0.55
G係数(再分配後) 0.36 0.38 0.38 0.39 0.38 0.38
再分配による改善度(%) 18 19 23 26 29 32
税金による改善度(%) 4 3 3 3 4 5
社会保障による改善度(%) 15 17 21 24 27 28
当初所得のG係数が年々増えているが,再分配後のG係数はほぼ一定である。15年間で再分配による改善度は18→32%で増えた。税金による改善度は変わらず,社会保障による改善度は15→28%で増えた。
上表の数値は厚労省の報告書から直接引用した。シンプソン法(台形法)を使うと再分配後のG係数で誤差が大きくなるからである。
当初所得 02年 05年 08年 11年
A尺度(ε=2) 0.96 0.96 0.96 0.95
実質A価(ε=2) 22万 19万 18万 23万
実質R価( =0.01) 127万 102万 96万 84万
下位30%点 180万 118万 116万 92万
実質R価( =0.1) 267万 233万 218万 197万
全国消費者物価指数(年平均)は14年=1
再分配後所得 02年 05年 08年 11年
A尺度(ε=2) 0.48 0.52 0.46 0.47
実質A価(ε=2) 306万 268万 280万 268万
実質R価(r=0.01) 246万 228万 223万 212万
下位30%点 314万 291万 228万 263万
実質R価(r=0.1) 369万 349万 330万 315万
全国消費者物価指数(年平均)は14年=1
ε=2のA価は下位10~30%の低所得者,r=0.01のR価は下位20~30%の低所得者,r=0.1のR価は下位35~40%の低所得者の所得を表す。これが庶民感覚の社会価値である。
下位30%点の実質所得は9年間で当初所得180→92万,再分配後314→263万と下がった。今の庶民は年92万円稼ぎ,再分配後の262万円で暮らしている。
ε=2のA尺度とA価は計算が簡単で便利である。だが,A尺度はG係数より精度が悪く,A価はR価より精度が悪く,経年変化がわからない。
当初所得の階級値は厚労省報告書第2表による。第1表では階級値がわからない。
再分配後所得の階級値は第1表による。1千万円未満では階級の中央を階級値とした。1千万円以上の階級値は,統計上の所得平均と計算による所得平均が一致する値と仮定し,1481→1412→1452→1430(万円)と推定した。
例3 厚労省「所得再分配調査」(個人)
格差の尺度 02年 05年 08年 11年
当初所得G係数 0.42 0.44 0.45 0.47
再分配後G係数 0.32 0.32 0.32 0.32
再分配による改善度(%) 23 26 30 33
税金による改善度(%) 2 4 5 6
社会保障による改善度(%) 21 23 26 29
当初所得A尺度(ε=2) 0.85 0.87 0.88 0.86
再分配後A尺度(ε=2) 0.36 0.39 0.34 0.35
当初所得のG係数が年々増えたが,再分配後のG係数はほぼ一定である。9年間で再分配による改善度は23→33%で増えた。税金による改善度は2→6%,社会保障による改善度は21→29%で増えた。
A尺度( =2)は計算が簡単で便利であるが,G係数より精度が悪く,経年変化がわからない。
G係数と改善度の数値は厚労省報告書第10表から直接引用した。シンプソン法(台形法)を使うと,再分配後のG係数で誤差が大きくなるからである。
A尺度の計算において,当初所得の階級値は厚労省報告書第8表による。第7表では階級値がわからない。再分配後所得の階級値は第7表による。800万円未満では階級の中央を階級値とした。800万円以上の階級値は,統計上の所得平均と計算による所得平均が一致する値と仮定し,1147→1102→1221→1206(万円)と推定した。
当初所得 02年 05年 08年 11年
実質A価(ε=2) 49万 41万 38万 42万
実質R価(r=0.01) 111万 95万 88万 81万
下位30%点 179万 154万 141万 118万
実質R価(r=0.1) 194万 175万 167万 156万
全国消費者物価指数(年平均)は14年=1
再分配後所得 02年 05年 08年 11年
実質A価(ε=2) 237万 218万 226万 221万
実質R価(r=0.01) 184万 174万 172万 170万
下位30%点 229万 220万 214万 209万
実質R価(r=0.1) 251万 242万 234万 231万
全国消費者物価指数(年平均)は14年=1
ε=2のA価は下位15~30%の低所得者,r=0.01のR価は下位15~25%の低所得者,r=0.1のR価は下位25~40%の低所得者の所得を表す。これが庶民感覚の社会価値である。
下位30%点の実質所得は9年間で当初所得179→118万,再分配後229→209万と下がった。今の庶民は年118万円稼ぎ,再分配後の209万円で暮らしている。
A価(ε=2)は計算が簡単で便利であるが,R価より精度が悪く,経年変化がわからない。
当初所得の階級値は厚労省報告書第8表による。第7表では階級値がわからない。
再分配後所得の階級値は第7表による。800万円未満では階級の中央を階級値とした。800万円以上の階級値は,統計上の所得平均と計算による所得平均が一致する値と仮定し,1147→1102→1221→1206(万円)と推定した。