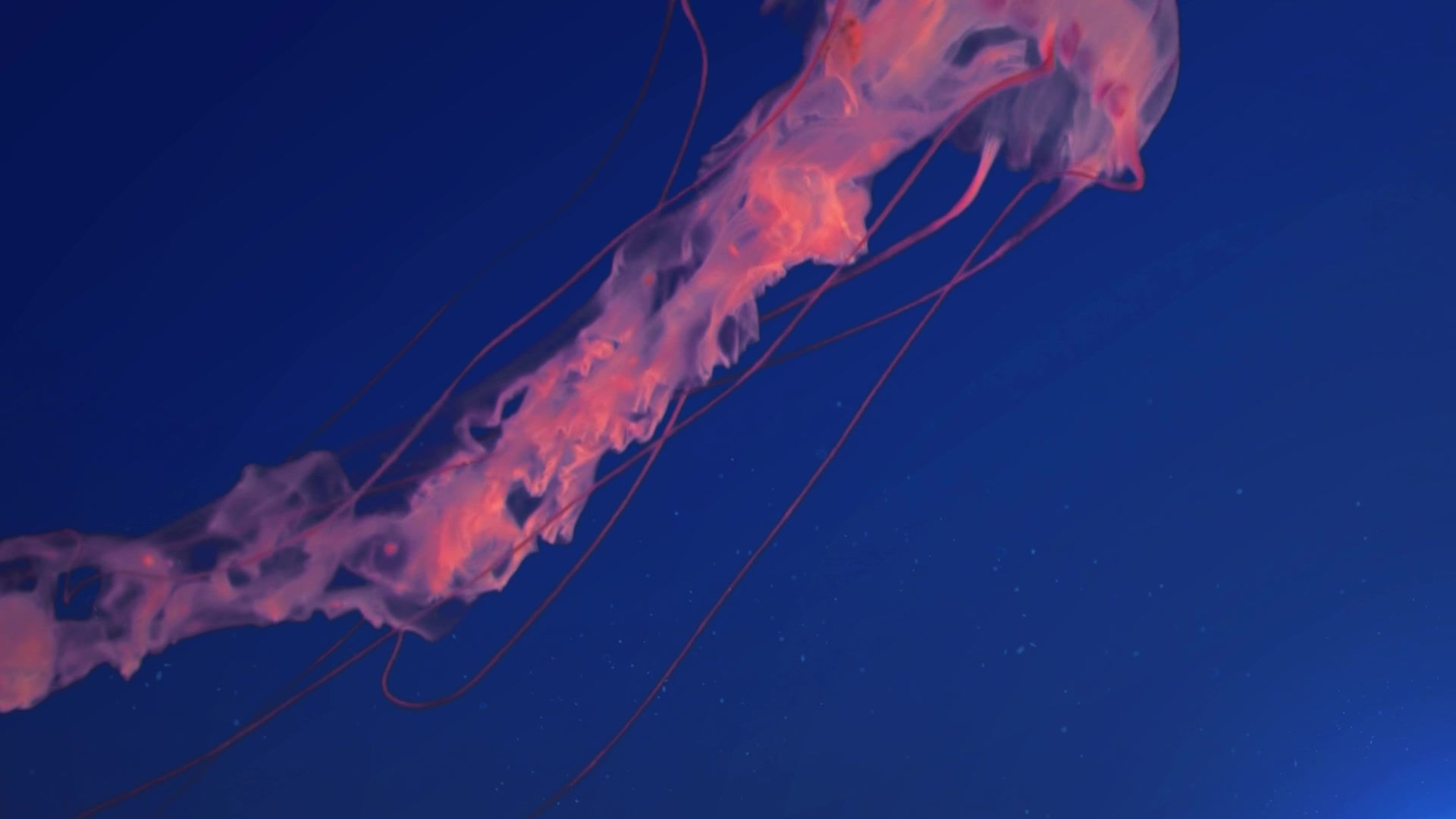
第2節 職業教育と生涯教育
学校歴に意味はない
職業教育は実学の一部である。たとえば,料理は家庭科(生活科学)に含まれ,実学に含まれる。料理人の卵にとっては職業教育である。
安倍晋三(首相)を議長とする産業競争力会議は15年6月,職業教育校を設置する方針を示した。16年に制度の内容を固め,19年度開校をめざす。学校は新設せず,既存の学校を職業教育校にする。
職業教育校の内容は,前年の14年10月に冨山和彦(経営共創基盤CEO)がすでに具体化している。
教育内容は文学部=シェイクスピア,文学概論→観光業に必要な英語,地元の歴史・文化の名所説明力,経済・経営学部=マイケルポーター,戦略論→簿記・会計,弥生会計ソフトの使い方,法学部=憲法,刑法→道路交通法,大型第二種免許・大型特殊第二種免許,工学部=機械力学,流体力学→トヨタで使われる最新鋭工作機械の使い方―に変わる。
教員は英文学=TOEIC,経営学=簿記会計2級指導や弥生会計ソフトによる財務三表作成,法学部=宅建やビジネス法務,工学部=最新鋭の工作機械の使い方―の指導を勉強し直す。
学校の評価は卒業生の就職率×初任給で決まる。
富田はG(global)とL(local)に分ける。だが,本来A(academic)の場である大学にG(global)もL(local)もない。就職活動の一環として勉強するG組とL組はP(professional)の学校に進むべきである。
医歯薬看護はG組である。日本人を治せる者は外国人も治せる。外国で災害が発生した時,医療関係者を派遣することはあり得る。
89年から13年の24年間で,12歳児の平均虫歯本数は4.30本から1.05本に減った。虫歯のある子どもの割合も90%超から40%台に減った(文科省調べ)。一方,60年代に3万人台だった歯科医は10万人を超えた。ゆえに,国内では歯科医が余る。だが,歯科医はG組である。国際歯科医の需要は無限に広がる。
理工農はすべてG組である。日本の車を作れる者は外国の車を作れる。高度な技術者を外国の工場に派遣することはあり得る。だが,組立工の派遣は現地の雇用を奪う。ゆえに,単純労働者はL組である。
外国の紛争解決に日本の弁護士や税理士を派遣しても役立たない。実務家はすべてL組である。
G組は職業大学校で高等職業教育を受けさせるか18歳の段階で企業の幹部候補生にすればよい。L組は職業教育を受けさせるか18歳で就職させて企業が育てればよい。
公認会計士予備校の慶應大,早稲田大・中央大は職業教育校(P)である。学問(A)の東大は簿記や会計ではなく経済理論を教える。東大の教員は簿記・会計を知らず,学生は教員の著書の消費者である。だが,東大から財務省に進むと税務大学校で初めて簿記・会計を習う。つまり,東大の教員がAで東大生はPである。法学部も,東大・中央大・明治大・法政大・早稲田大・日本大は明治後期の六大法律学校であり,Pである。
今の学生は就職準備と教員の雇用対策のためにいる。現職教員の解雇につながるような急激な改革は避けなければならない。ゆえに,再編には20年かかる。
富田は「ごく一部のTop Tier校・学部以外は職業訓練校(職業教育校)にするべきだ」と言う。富田は「職業教育(P)より学問(A)が上」「地元(L)より世界(G)が上」と考えているようである。だが,実社会を支えているのは間違いなく地元の職業人である。A,G,Lは社会的な役割であって優劣ではない。
コンテンツ(学問歴,資格)よりもパッケージ(学校歴)を重視する人は無能である。A組は学問歴,G組とL組は資格が重要である。生涯教育は参加することに意義がある。
仏は職業教育偏重
数学者ルネ・トムはENS出身である。歴代の大統領はミッテランもシラクもオランドもシアンスポからのエナルクである。
フランスのエリートは大学(université)に行かない。まずは高校併設のクラス・プレパラトワール(準備学級)に進む。プレパ生は「もぐら」と呼ばれ,「太陽を見る時間がない」ほど猛勉する。2年間のプレパを終えるとグランゼコール(職業大学校)のコンクール(入試)を受ける。グランゼコールに入れない者は大学に進む。
医師,弁護士,聖職者をめざす者は大学の職業系学部に進む。バカロレアを取得すれば医学部でもどこでも入れるが,進級は難しい。進級できなければ留年,学部変更,他大学編入,退学などとなる。
フランス革命の頃,社会資本整備のために技術者や教育者が必要となり,理工系の国立土木学校(ポンゼショセ),パリ国立高等鉱業学校(ミン),エコール・ポリテクニーク(X=イクス)と教育系の高等師範学校(ENS)が設立された。
ESCP EUROPE(旧パリ高等商業学校),HECパリ,ESSECなどの商業系は19世紀以後である。数か月の企業インターンがある。ESSECでは米国のMBAも取得できる。
国立行政学院(ENA)は第二次大戦直後に設立された。政官エリートはパリ政治学院(シアンスポ)で5年間学んだ後,ENAを受験する。インターンは大使,知事,大都市の市長,大企業経営者などから直接研修を受ける。コンクール(卒試)では多数の試験官が1人の学生を取り囲むように質問する。卒業生はエナルクとよばれ,政官界で活躍する。
卒業後,ENAから政官界,商業系から大企業に進む者が多い。イクスからは多様な世界に進む。大企業の幹部はイクス,ENA,HECパリ出身者が多い。
フランスのエリートは実学系(P)であり,グランゼコールと大学の医学部に偏在する。学術系(A)のエリートは少なく,大学の研究水準は低い。
以下は,上海交通大学高等教育研究院2015,英国の評価機関クアクアレリ・シモンズ(QS)2015-2016,英誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)2015-2016の順位である。
ENSパリ(72位,23位,54位),イクス(-,40位,-),パリ第6(36位,-,-),パリ第11(41位,-,-),ストラスブール大(87位,-,-)で,日本の東大(21位,39位,43位),京大(26位,38位,88位),大阪大(85位,58位,-),名古屋大(77位,-,-),東京工業大(-,56位,-),東北大(-,74位,-)より劣る(-は百位圏外)。
サウジアラビアの世界大学ランキングセンター(CWUR)2015の評価では財界で活躍するイクスが36位,教育の質が高いENSパリが37位である。
CWUR評価の25%はフォーブスが選ぶ2千社のCEOの割合が占めている。つまり,学術面の評価ではない。政官界で活躍するENAも圏外であり,実学全般の評価でもない。日本の慶應大が34位,早稲田大が38位である。学術面での実績がなくても大企業の社長が多ければ上位となる。
米仏の違いは費用負担
受益者負担の米国にアメリカンドリームはない。学生は授業料を払うために多額の借金をし,卒業後十数年かけて返す。
一方,フランスでは大学の授業料は無料で,学生は若干の登録料のみ負担する。年間の登録料は学部181ユーロ(2万3千円),修士250ユーロ(3万2千円),博士380ユーロ(4万9千円)と安い。社会保険料百ユーロ(1万3千円)と合わせても安い。
グランゼコール(職業大学校)の場合,理工系の多くは公立であり,登録料も年千ユーロ(13万円)未満である。商業系は私立が多く,年7~8千ユーロ(百万円)と高いが,多くを企業が負担する。128円/ユーロ
国立行政学院(ENA)の学費は全額国が負担する。学生は準公務員として給料をもらう。その点は日本の大学校と変わらない。
高等教育の目的
学問の自由は誰にでもあるが,能力と目的によって進路が分かれる。学問(academic)のA,世界(global)のG,地元(local)のL,趣味(hobby)のHである。GとLは職業(professional)のPである。論理的思考力が必須のA組とG組は数学による選抜が必要である。
たとえば,野球を楽しむ自由は誰にでもあるが,甲子園に出場してプロ野球選手になるのはエリートだけである。一般の人は観戦や草野球を楽しむ。
たとえば,将棋を楽しむ自由は誰にでもあるが,奨励会に入り,棋士となるのはエリートだけである。一般の人は仲間と対戦したり,棋士のファンとなる。
能力による入学制限はプラトンが始めた。アカデメイアの門には「幾何学を知らざる者は入るべからず」とある。今でも,形式論理学がわからなければ弁証法はわからず,ユークリッド幾何学がわからなければ非ユークリッド幾何学はわからない。
生涯教育←職業教育
知的好奇心を満たそうとするH組の多くはP組である。昼間働いて夜学に通う。余暇に放送大学で学ぶ。職業人としての役割を果たし,自らの努力で時間と金をつくり,受益者負担で生涯教育を受ける。その学費は間接的にA組の雇用を支える。
野球に例える。昼間働いてナイターを観戦する。観戦はプロ球団,メディア,スポンサーを支え,間接的にプロ選手を支えている。平日働いて日曜に草野球を楽しむ。就職して都市対抗に出る。還暦野球で現役世代と年金世代が交わる。
将棋に例える。昼休み,終業後,休日に仲間と戦う。余暇は棋士の情報整理を楽しむ。情報収集は主催新聞社や専門誌出版社を支え,間接的に棋士を支える。その源泉は日頃の労働である。
論理的思考力は若くして確定する。数学や将棋が20歳過ぎてから急に強くなる例は少ない。一方,情報の体系化は年を重ねるほど有利である。20代前半で完成する人文科学はない。
古代ギリシアでは自由人は奴隷のおかげで学問に専念できた。平安時代は農民のおかげで文学が発展した。昭和まで,女性が家事労働を担い,高等教育は男が独占した。だが,今は平等の時代である。学問に専念する階級や性別は要らない。
情報の整理をネットが担う今,受験に暗記は不要である。暗記型の人材は学問(A)ではなく職業教育(P)に進み,まずは職業人としての役割を果たすべきである。情報整理型の勉強は生涯学習や趣味でやればよい。